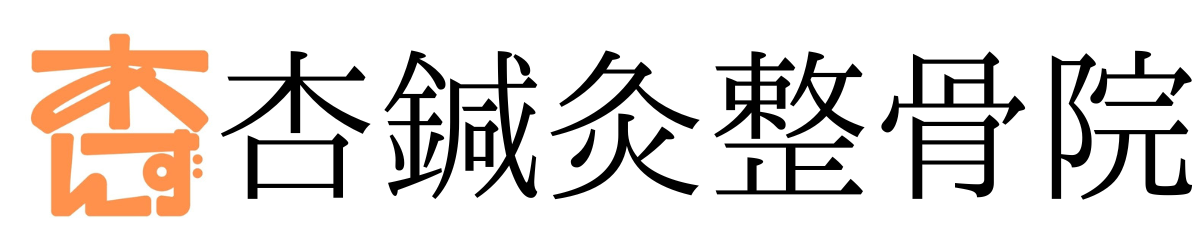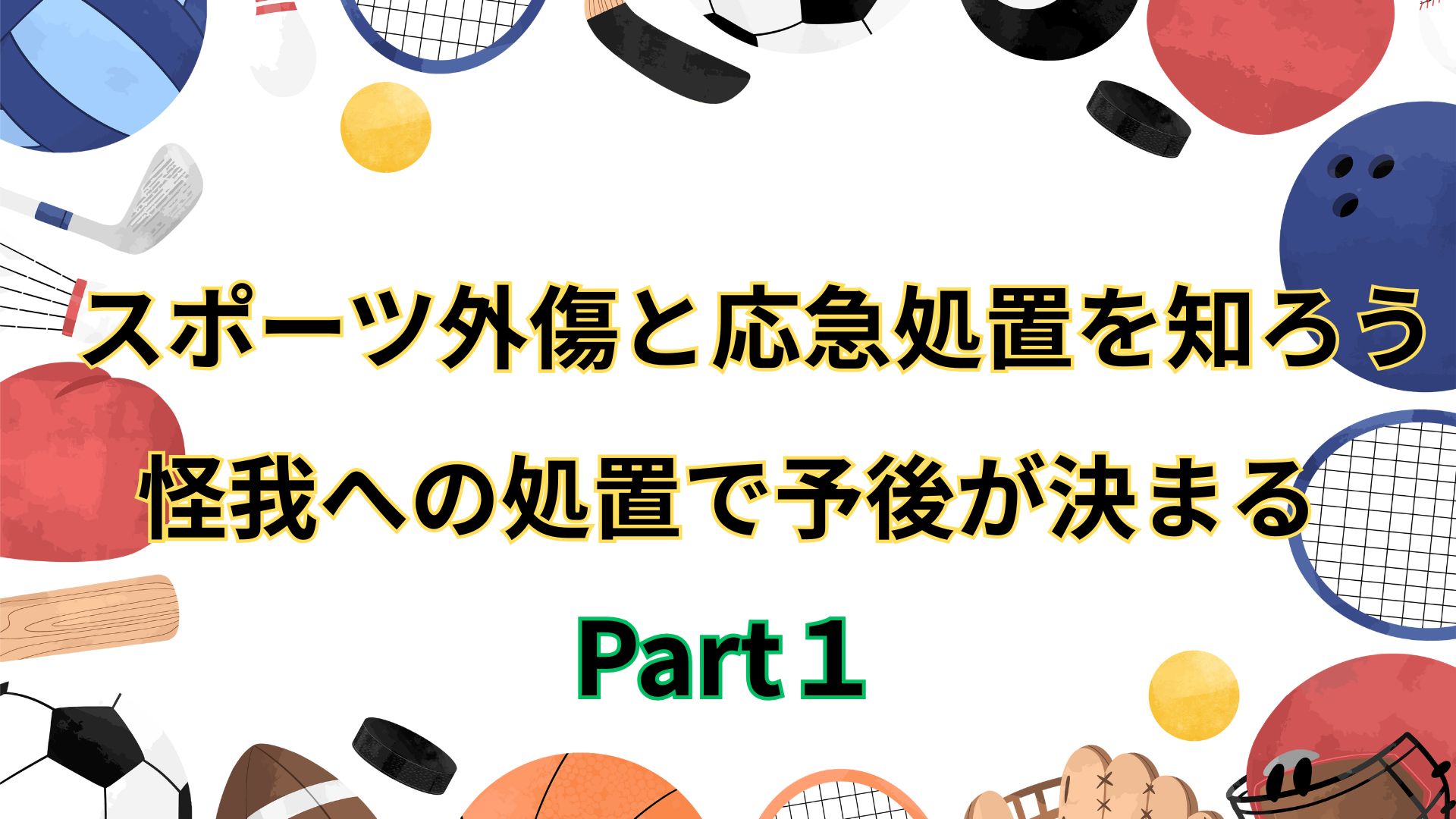
こんにちは!!
福岡県筑紫野市二日市にある杏鍼灸整骨院の妹川(いもかわ)です。
今回は【スポーツ外傷と応急処置を知ろう|怪我への処置で予後が決まる!Part1】に関して紹介していきます。
今回はPart1とPart2の二部構成になっています。
怪我の種類の説明と怪我をした時に行ってほしい応急処置は、とても大切な事なので少し内容が多くなってしまいました。
そのためPart1では応急処置の話しに入る前にスポーツ外傷に関して知っていただきましょう。
怪我に関して知る事は怪我をする側にとっても処置をする側にとってもどちらにとっても凄く大切な事なので、怪我をする理由から怪我の違いまでを少し話しをしていきます。
Part2では怪我に対する応急処置の説明をしていますので、こちらから確認してください。
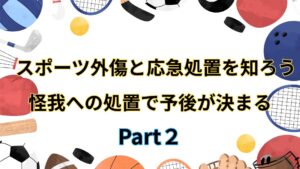
スポーツの現場では怪我はいつ起きてもおかしくない状況だと思います。
実際に選手は全力を出して頑張っているので、怪我をするかしないかは紙一重の所で競技をしていると思います。
このような状況の中で選手は競技をしているので、怪我は起きる前提で考えていて良いと思います。
そこで大切になってくるのが❝どのような怪我をしたのか❞という事と❝怪我が起きた時にどのように対処をしていくか❞という事です。
この事をしっかりと把握出来ているかどうかで、その後の競技復帰に大きく影響をしてくると思っています。
そこでまずはスポーツ外傷とは何かという事とスポーツ外傷による怪我に関して知っていきましょう。
スポーツ外傷とスポーツ障害とは??怪我の違いに関して知ろう
最初に《スポーツ外傷》とは何なのかに関して少し知っていきましょう。
また似たような言葉で《スポーツ障害》という言葉もありますよね。
実際には全然違うものなのでしっかりと理解できると良いと思います。
《スポーツ外傷》
スポーツ外傷とはスポーツ中に瞬間的な強い外力によって起こる怪我の事をいう
(捻挫・打撲・肉離れ(挫傷)・骨折・脱臼など)
《スポーツ障害》
スポーツ障害とはスポーツ中の繰り返しの弱い外力やオーバーユースによって起きる怪我の事をいう
(〇〇腱炎や腱鞘炎・疲労骨折・ジャンパーズニー・テニス肘など)
どちらもスポーツ活動中に起きる怪我ですが、怪我が起きる原因や症状は大きく違います。

スポーツ外傷は身体の外から受ける強い力によって損傷を起こしてしまう事です。
例でいうと足関節捻挫の場合は足首を捻った時に体重がかかる事によって関節に大きな力が加わってしまいます。
その時に関節周りにある靭帯が関節の過剰な動きに耐えられずに切れてしまいます。
骨折や脱臼も同様で手を転倒で手をついた時の捻転力やぶつけた時の外力によって、折れたり脱したりしてしまいます。
これらのように一回に強い力が加わったことによって起きてしまうのがスポーツ外傷で、外力の強さや方向や捻じれ具合によっては大きな怪我になりやすいのも特徴です。
また怪我が大きければ大きいほど競技から離れる期間が長くなるために怪我をした所が元の状態に戻っていくのに時間がかかりやすいです。
基本的には怪我をした部分は安静にしている事でしっかりと治っていきます。
しかし怪我の程度が大きく治るのに時間がかかればかかるほど周りの筋肉などの組織は弱くなったり働き・動きが悪くなるために、これらを改善させていく事も必要になってきます。
この改善がしっかりと出来ていないと、再負傷を起こしたりスポーツ障害を起こしたり、怪我は治っていても今まで通りのパフォーマンスが出来なかったりと、運動をしていく上ではマイナスな事が起きやすいです。
そのためスポーツ外傷の場合は、怪我の治っていく過程と一緒にその周りの組織のリハビリを行って改善を行っていく事が大切です。

スポーツ障害は繰り返しの負荷によって起きる怪我なので、一回の負荷で起きる事はありません。
上に説明しているように、もともと練習でかかる負荷が何度も重なったりしても起きますが、他にも起きやすい理由があります。
それはフォームや癖など局所に負荷が掛かりやすい状態になっている事や、扁平足やニーイントゥーアウトのように自分も気付かないうちに負荷の掛かりやすい姿勢をとってしまっている事です。
これらの状態のまま運動を繰り返す事によって負荷の掛かりやすくなっている場所が微細な損傷を繰り返すので炎症や痛みを起こしていきます。
ではこのように起きてきた症状を改善していくためにはどうしたらいいでしょうか??
スポーツ障害の場合は、ただ運動を休んで痛みが無くなればOKという訳では無く、痛みが出ている所に負荷をかけている理由をしっかりと突き止めていく事が大切です。
そして理由の改善をしていく事で症状は軽減しやすくなりますし繰り返し痛める可能性も低くなっていきます。
そのためスポーツ障害の場合は痛みや炎症を引かせていく事と並行して、痛みや炎症を起こしている部位に負担をかけている理由の改善を起こしていく事が大切になります。
このようにスポーツ外傷とスポーツ障害は起きる機序から怪我の内容まで全然違います。
そのため自分に起きている怪我を知る事はとても大切で❝この怪我はどこを損傷していて何が原因で起きているのか❞を考える事で、スポーツ外傷の場合は応急処置の方法を考えられますし、スポーツ障害の場合は怪我を起こさないための対策を考える事が出来ます。
スポーツ外傷に関してもっと知ろう|スポーツの種類と怪我の種類
スポーツ外傷とスポーツ障害に関して説明しましたが、今回Part2の方で紹介している内容はスポーツ外傷が起きた後に行ってほしい応急処置です。
スポーツ外傷は基本的にコンタクトスポーツで起きやすいですが、接触や転倒した際は動き方が予測できないために様々な怪我になりやすいです。
またコンタクトスポーツでなくても強い捻転力や圧迫力や筋収縮力など、他の外力が強く働く事によって起きる事も多くあります。
これらは様々なスポーツで様々な場面で起きています。
そこでスポーツ外傷とはどのような怪我があるのかもう少し説明していきましょう。

《足関節》
足関節の損傷は足関節捻挫による靭帯損傷が一番多い
内側靭帯(三角靭帯)や外側靭帯(前距腓靭帯・後距腓靭帯・踵腓靭帯)を損傷する事が多く、その中でも前距腓靭帯の損傷が最も多い
また捻挫と伴って足関節部の骨折(内果骨折・外果骨折・第五中足骨骨折など)を併発する可能性もある
◉起こしやすいスポーツ
どのスポーツでも起こしやすい怪我の一つ
バレーボール・バスケットボール・サッカー・ラグビーなど
《膝関節》
膝関節はジャンプの着地や接触プレー時に相手が上に乗ったりなど膝関節に強い捻転力が働いて靭帯損傷や半月板損傷を起こす事が多い
側副靭帯(内側・外側)や十字靭帯(前・後)や半月板の損傷を起こしやすい
この中でも内側側副靭帯・内側半月板・前十字靭帯を一緒に損傷する場合も多い(不幸の三徴候)
転倒時に直達外力により膝蓋骨骨折を起こす事もある
◉起こしやすいスポーツ
柔道・ラグビー・バレーボール・バスケットボール・サッカー・野球など
《肘関節》
肘関節は強く捻転力や過伸展の力がかかる事で靭帯損傷や骨折を起こす事が多い
側副靭帯(内側・外側)・上腕骨遠位端骨折・橈骨頭骨折・肘頭骨折・肘関節脱臼などを起こす
多くは転倒時に手をついて損傷したり、コンタクトスポーツでは他の選手が上に乗る事で起きる事もある
また手の着き方によっては脱臼・骨折をする場合もある
◉起こしやすいスポーツ
柔道・ラグビー・サッカー・野球など
《手指》
手指は球技で突き指をして靭帯損傷や骨折や脱臼を起こす事が多い
靭帯損傷を単独で起こす事が多いが、外力が強い場合には靭帯損傷と一緒に骨折や脱臼を起こす可能性もある
◉起こしやすいスポーツ
バスケットボール・バレーボール・ハンドボール・野球など
《肉離れ(挫傷)》
筋肉であればどこでも起こす可能性がある
多くは大腿部やふくらはぎなど大きな筋肉に起きる事が多く、その多くが遠心性収縮時に起きる
競技によって起きる場所が変わりやすい
◉起こしやすいスポーツ
陸上競技(ハムストリングス)・サッカー(大腿四頭筋)・テニス(下腿三頭筋)・ウエイトリフティング(大胸筋)など
《腱断裂》
主にはアキレス腱断裂が知られているが上腕二頭筋腱断裂などもある
発生機序は肉離れと一緒で遠心性収縮時に起きるが、筋の損傷がなく腱に強く負担が掛かった場合に腱断裂を起こす場合がある
◉起こしやすいスポーツ
アキレス腱:剣道・バドミントン・テニスなど
上腕二頭筋腱:野球・テニスなど
《打撲》
コンタクトスポーツで相手との接触が多い競技であればどこにでも起きやすい
大腿部や下腿部など打撲を受けた場所によっては痛みが強く競技が出来ない場合もある
また打撲部には内出血が必ず起きているので注意が必要
◉起こしやすいスポーツ
ラグビー・サッカー・バスケットボール・柔道・剣道など
少しだけ起きやすい怪我を挙げていきましたが、怪我はもっと沢山ありますし、起きるスポーツもこれらに限った事ではありません。
冒頭にも書いていますがスポーツの現場では、怪我はいつ起きてもおかしくないですし、どんな怪我が起きてもおかしくないと思っています。
それくらい選手はギリギリの所で頑張っているのだと思います。
スポーツ現場の中で怪我を判断するのはとても難しいですし、分かりにくい事も予想がしにくい事も多くあります。
しかし、そんな状況に中で『足首の怪我??大丈夫!!』など、知らないで簡単に判断をする事はとても怖くて非常に危険な事です。
そのため『足関節には〇〇の怪我の可能性がある』など様々な可能性が頭に入っている事がとても大切だと思っています。
Part1のまとめ
今回は【スポーツ外傷と応急処置を知ろう|怪我への処置で予後が決まる!Part1】に関して紹介しました。
今回のPart1ではスポーツ外傷に関しての知識と、その時に起きやすい怪我に関して少し知っていただきました。
Part2ではスポーツ外傷が起きた時に行う応急処置に関して説明していますので一緒に読んでください。
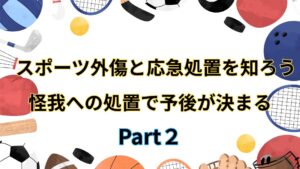
スポーツの現場では色々な怪我を起こしやすいです。
そこで❝どのような怪我をしたのか❞を考える事はとても大切ですし、怪我が分からない場合でも❝どのような怪我をした可能性があるか❞と考える事もとても大切です。
スポーツをしている選手は紙一重の所で頑張っているので、怪我をしても競技を続けようとするのは多くあると思います。
そこで選手を守る事が出来るのは、周りにいる監督の方やコーチの方やトレーナーや保護者の方々です。
そのためにも怪我に関する知識や、Part2で話している怪我が起きた時の応急処置に関しての知識を身につける事はとても大切です。
選手のためにも今回の記事が少しでも役に立てるといいなと思います。
杏鍼灸整骨院の妹川でした。
またなにか怪我に関してやテーピング方法など疑問がある方は気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 柔道整復師
-
柔道整復師
福岡柔道整復専門学校(現 福岡医療専門学校)卒業
陸上競技、サッカー、バレーボール、柔道、剣道など様々なスポーツチームの帯同経験多数
最新の投稿
 テーピング2026年1月17日アキレス腱痛に対する保護テーピング|キネシオテープ
テーピング2026年1月17日アキレス腱痛に対する保護テーピング|キネシオテープ テーピング2025年12月17日手首の痛み!!フィギュアエイトテープの手首への応用
テーピング2025年12月17日手首の痛み!!フィギュアエイトテープの手首への応用 テーピング2025年12月11日腹筋の肉離れ!!リンパファンテープで腫れ改善!!
テーピング2025年12月11日腹筋の肉離れ!!リンパファンテープで腫れ改善!! テーピング2025年12月8日足関節の固定!!ホワイトテープの巻き方
テーピング2025年12月8日足関節の固定!!ホワイトテープの巻き方