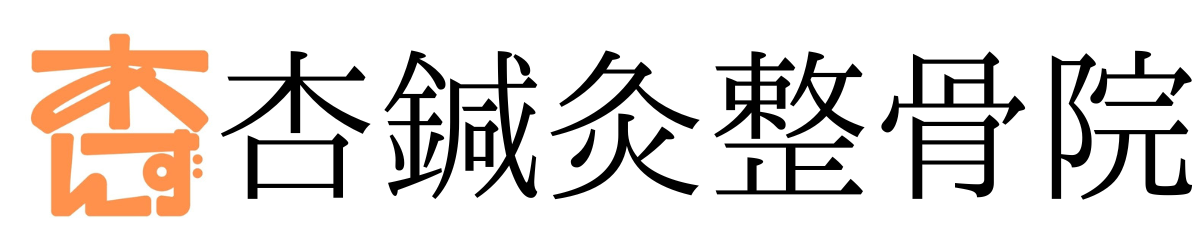こんにちは!筑紫野市二日市にある杏鍼灸整骨院の陣内です。
今回は肉離れに対する鍼灸の効果の可能性をご紹介していきたいと思います。
スポーツや日常生活で起こる肉離れ。筋肉が傷ついて痛みを伴う、誰にでも起こりうる怪我です。実は高齢者のスポーツ関連の怪我のうち、約40%が骨格筋の損傷だと言われています。
肉離れが起きると、筋肉は自然に修復しようとしますが、完全に元通りになることは意外と難しいのです。傷ついた部分に硬い線維(せんい)のような組織ができてしまい、これを「筋線維化(きんせんいか)」と呼びます。この線維化が起こると、筋肉の動きが制限されてしまい、運動能力が低下してしまうことがあります。
そこで注目されているのが、「鍼通電(はりつうでん)」という治療法です。鍼に弱い電気を流すこの治療法が、なぜ肉離れの回復に効果があるのか。
今回は、最新の研究をもとに、その仕組みをできるだけわかりやすくお伝えしていきます。
肉離れが起きると、筋肉の中で何が起こっているの?

筋肉の修復プロセス
肉離れが起きると、筋肉の中では次のような変化が起こると考えられています。
まず、傷ついた部分に炎症が起こります。これは身体が「ここを治さなければ!」というサインを出している状態です。この炎症反応は、修復のためには必要なものなのですが、長く続きすぎると問題になることもあります。
次に、修復の段階に入ります。ここで登場するのが「マクロファージ」という免疫細胞です。マクロファージは、いわば身体の中の「掃除屋さん兼修理屋さん」のような存在です。
マクロファージの二つの顔
マクロファージには、実は二つのタイプがあると考えられています。
M1タイプのマクロファージは、炎症を引き起こす物質を出します。これは怪我の初期段階では大切な働きなのですが、ずっと続くと炎症が長引いてしまいます。まるで火事の現場で警報を鳴らし続けているような状態です。
一方、M2タイプのマクロファージは、炎症を抑える物質を出して、組織の修復を助けます。こちらは消火活動をして、後片付けをしてくれる存在と言えるでしょう。
理想的には、怪我の初期にM1タイプが働き、その後M2タイプに切り替わって、スムーズに修復が進むことが望ましいと考えられています。ところが、このバランスが崩れると、修復がうまくいかなくなってしまうのです。
線維化の問題
修復がうまくいかないと、「コラーゲン」というタンパク質が過剰に作られることがあります。コラーゲンは本来、組織を支える大切な成分なのですが、多すぎると筋肉が硬くなってしまいます。
これはまるで、壊れた道路を修理するときに、必要以上にコンクリートを使いすぎてしまったような状態です。道路は塞がれましたが、硬くて動きにくくなってしまう。これが筋線維化という現象なのです。
鍼通電は何をしているの?

鍼通電の基本
鍼通電とは、身体の特定のツボ(経穴)に鍼を刺し、そこに弱い電気を流す治療法です。研究では、ラットの「腎兪(じんゆ)」と「足三里(あしさんり)」というツボに鍼を刺し、1日20分間、週に数回の治療を行ったそうです。
電気といっても、ごく弱いもので、痛みを感じるほどではありません。むしろ、筋肉に心地よい刺激を与えるようなイメージです。
炎症を和らげる効果
研究の結果、鍼通電を行った動物では、炎症が明らかに軽減されたことが観察されました。
具体的には、炎症を引き起こす物質(IL-6、IL-4、TNF-αなど)の量が減り、逆に炎症を抑える物質(IL-33、IL-10など)が増えたそうです。これは、身体の炎症反応がうまくコントロールされている証拠だと考えられています。
例えるなら、騒がしかった工事現場が、徐々に静かで秩序ある作業場に変わっていくような感じです。必要な作業は続けながら、余計な騒音は減っていく。そんなイメージですね。
マクロファージのバランスを整える
さらに興味深いことに、鍼通電はマクロファージのバランスにも影響を与えることがわかりました。
治療を行った動物では、M1タイプからM2タイプへの転換が促進されたと考えられています。つまり、「炎症を起こすモード」から「修復するモード」へのスイッチが、よりスムーズに行われるようになったということです。
これは特に治療開始から7日目に顕著だったそうです。早い段階で適切なマクロファージのバランスが整うことは、その後の修復過程にとって非常に重要だと考えられています。
線維化を抑える効果
鍼通電の最も注目すべき効果の一つが、過剰な線維化を抑えることです。
研究では、治療を行った動物の筋肉組織を顕微鏡で観察したところ、コラーゲンの沈着が明らかに少なかったそうです。また、線維化に関連するタンパク質(Axin2、β-カテニン、コラーゲンIIなど)の量も減っていました。
これは、道路の修理に例えると、必要な分だけコンクリートを使って、きちんと機能する道路に仕上げたような状態です。硬くなりすぎず、柔軟性を保ちながら、強度も確保されている。そんな理想的な修復が行われたと考えられるのです。
鍼通電が効果を発揮する仕組み
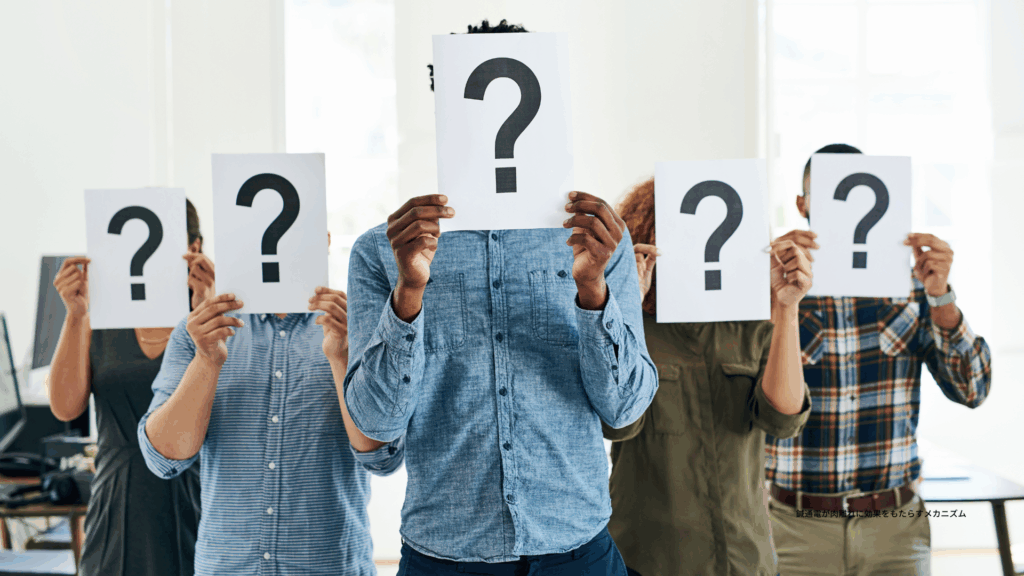
TGF-β1という重要な因子
ここからは少し専門的なお話になりますが、できるだけわかりやすく説明していきます。
筋肉の線維化には、「TGF-β1(トランスフォーミング増殖因子ベータ1)」という物質が深く関わっていると考えられています。これは身体の中で様々な役割を持つ物質ですが、多すぎると線維化を促進してしまうのです。
TGF-β1は、まるで工事現場の現場監督のような存在です。適切な量であれば、修復作業を指揮してくれますが、過剰になると「もっとコンクリートを使え!」と指示を出しすぎてしまうのです。
細胞内のシグナル伝達経路
TGF-β1が働くと、細胞の中で「Smad3」「p38」「ERK1/2」といった物質が活性化されます。これらは細胞内の情報伝達システムの一部で、いわば「伝言ゲーム」の役割を果たしています。
研究の結果、鍼通電を行うと、次のような変化が観察されました。
- TGF-β1の量が減少
- p38の活性化が抑制
- ERK1/2の活性化が促進
- Smad3の活性が調整される
これらの変化は、線維化を抑える方向に働くと考えられています。つまり、鍼通電は細胞内の情報伝達システムに働きかけて、「線維を作りすぎないで」というメッセージを送っているのかもしれません。
MMPという酵素の役割
もう一つ重要なのが、「MMP(マトリックスメタロプロテアーゼ)」という酵素群です。これらは組織のリモデリング、つまり「作り直し」に関わる酵素です。
特にMMP-2とMMP-7は、筋肉の再生に重要な役割を果たすと考えられています。研究では、鍼通電によってこれらの酵素の活性が適切に調整されることが示されました。
これは建築に例えると、古い建材を取り除いて、新しい材料で作り直す作業に関わる職人さんのようなものです。鍼通電は、この職人さんたちの働きを調整して、より良い修復を促すと考えられているのです。
治療の効果は時間とともにどう変わるの?

7日目の変化
研究では、治療開始から7日目と14日目の変化を観察しました。
7日目の時点で、すでに炎症の軽減が見られたそうです。また、マクロファージのM1からM2への転換も始まっていました。これは、修復の基礎が整い始めた段階だと言えるでしょう。
14日目の変化
14日目になると、効果がさらにはっきりと現れたそうです。炎症を抑える物質の増加が顕著になり、線維化を示す指標も改善していました。
これは、治療の効果が時間とともに積み重なっていくことを示しています。一度や二度の治療ですぐに劇的な効果が出るわけではなく、継続的な治療によって、徐々に身体が本来持っている修復力を引き出していくのだと考えられます。
私たちの身体が持つ治癒力
自然治癒力を助ける治療
ここまでお読みいただいて、鍼通電が何か特別な物質を注入するわけではないことに気づかれたかもしれません。
そうなのです。鍼通電は、私たちの身体が本来持っている治癒力を、最適な状態に導くことを目指していると考えられます。
私たちの身体は、傷を治す素晴らしい能力を持っています。ただ、時にはそのプロセスがうまく働かないことがあります。炎症が長引いたり、過剰に線維化が進んだり。鍼通電は、そうした身体のバランスを整える助けをしているのかもしれません。
全体的なアプローチ
興味深いのは、鍼通電が一つの仕組みだけに働きかけるのではなく、複数のメカニズムに同時に影響を与えているらしいという点です。
- 炎症のコントロール
- マクロファージのバランス調整
- 線維化の抑制
- 細胞内シグナル伝達の調整
これらすべてが同時に、そして調和的に働くことで、効果を発揮していると考えられています。
これは、オーケストラの指揮者のような役割かもしれません。個々の楽器(身体の仕組み)はそれぞれ演奏できますが、指揮者がいることで、より美しいハーモニーが生まれる。鍼通電は、そんな調整役を果たしているのかもしれないのです。
日常生活への応用
どんな人に役立つ?
この研究結果は、次のような方々にとって希望となる可能性があります。
- スポーツで肉離れを起こした方
- 筋肉の怪我が治りにくいと感じている方
- 慢性的な筋肉の痛みや硬さに悩んでいる方
- リハビリテーションの効果を高めたい方
ただし、この研究は動物実験であることを忘れてはいけません。人間での効果は、さらなる研究が必要だと考えられています。
まとめ
肉離れという身近な怪我について、鍼通電がどのように効果を発揮する可能性があるのか、最新の研究をもとにお話ししてきました。
鍼通電は、次のような複数のメカニズムを通じて、筋肉の修復を助けていると考えられています。
- 炎症の適切なコントロール: 過剰な炎症を抑えながら、必要な修復反応は維持する
- マクロファージのバランス調整: M1タイプからM2タイプへの転換を促進する
- 線維化の抑制: 過剰なコラーゲンの沈着を防ぎ、柔軟性を保つ
- 細胞内シグナルの調整: TGF-β1/Smad3/p38/ERK1/2経路を通じて、修復プロセスを最適化する
これらの効果は、私たちの身体が本来持っている治癒力を引き出し、サポートすることで実現されていると考えられます。
鍼通電は、数千年の歴史を持つ東洋医学の知恵と、現代の科学的な理解が融合した治療法だと言えるでしょう。今後のさらなる研究によって、そのメカニズムがより明らかになり、より多くの方々の健康に役立つことが期待されます。
肉離れや筋肉の怪我でお悩みの方は、この記事が治療法を考える上での一つの参考になれば幸いです。ただし、実際の治療については、必ず医療専門家にご相談くださいね。
また怪我に関してやテーピング方法など疑問がある方は気軽にご相談ください。
参考文献
本記事は、以下の研究論文を主な情報源として作成しました。
Han H, Li H, Li H, Li M. (2021). “Electroacupuncture regulates inflammation, collagen deposition and macrophage function in skeletal muscle through the TGF-β1/Smad3/p38/ERK1/2 pathway.” Experimental and Therapeutic Medicine, 22(6), Article 10892.
この研究は、ラットを用いた動物実験により、鍼通電が骨格筋損傷後の炎症、コラーゲン沈着、マクロファージ機能に与える影響を調査したものです。TGF-β1/Smad3/p38/ERK1/2シグナル伝達経路を介したメカニズムが明らかにされており、鍼通電療法の科学的根拠を示す重要な研究となっています。
本記事の内容は、現時点での科学的知見に基づいていますが、医学研究は日々進歩しています。具体的な治療方針については、必ず医療専門家にご相談ください。
投稿者プロフィール

- 柔道整復師、鍼灸師
-
院長 柔道整復師 鍼灸師
福岡医健専門学校卒業
株式会社セイリン様、株式会社伊藤超短波などでもセミナー活動をしており精力的に鍼灸をひろめようと活動もしております。
陸上競技、ソフトボール、バレーボール、柔道、剣道など様々なスポーツチームの帯同経験多数
最新の投稿
 お知らせ2025年12月29日年末年始お知らせ
お知らせ2025年12月29日年末年始お知らせ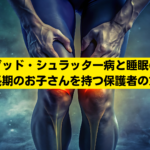 お知らせ2025年12月22日オスグッド・シュラッター病と睡眠の関係|成長期のお子さんを持つ保護者の方へ
お知らせ2025年12月22日オスグッド・シュラッター病と睡眠の関係|成長期のお子さんを持つ保護者の方へ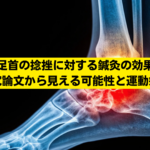 鍼灸治療2025年12月20日足首の捻挫に対する鍼灸の効果:研究論文から見える可能性と運動療法
鍼灸治療2025年12月20日足首の捻挫に対する鍼灸の効果:研究論文から見える可能性と運動療法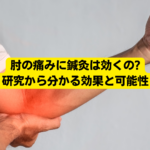 鍼灸治療2025年12月19日肘の痛みに鍼灸は効くの?研究から分かる効果と可能性
鍼灸治療2025年12月19日肘の痛みに鍼灸は効くの?研究から分かる効果と可能性